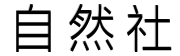好き嫌いの感情で物事の善悪を
決めていることが多い
物事の善悪の判断を下すときは、それが本当に正しいことか間違っていることかが問題であって、自分の気に入るか気に入らないかで決めてよいはずはありません。にもかかわらず、知らず知らず好き嫌いで善悪を判断していることが、非常に多いようです。
例えば、ある政党を好きになったため、少々間違った政策を取っていると思っても自分流に解釈を加えて見過ごしたり、嫌っているために、その政策の良いところまで無視したりするようなことがあったりします。
このいずれも「好む感情」「嫌う感情」のため、あえて物事の本質にふれようとしていないのです。このように、好き嫌いの感情は単なる好き嫌いにとどまらず、善悪感情にまで発展していることが少なくありません。
好きとか嫌いというのは何が根拠になっているか、また何を標準にしているか。それは個人の感情的な好みに合うか、合わないかであり、自分にとって都合がよいか、悪いかに他なりません。
「だから自分は好きだ」と思うことも、他人には嫌いなことであったり、「嫌いだ」と思うことも他人から見れば好ましいものであったりします。このことがよく分かったら「好き嫌い」を「善悪」と結びつける誤りは避けることができるはずです。
◎
事に当たって自分のありのままの心の動きを客観することによって、物事の本質にふれ、真実を知る心の眼が開けてきます。そして、より深く自分自身を知ることで、好き嫌いの感情を超えて、新たに人間をはじめあらゆる物事に対して思いやりの心が生まれてきます。更には、人と人とのつながり、また物と人とのつながりを、大切に生きていくことができるようになります。
好き嫌いは、多かれ少なかれだれにでもあることですから、当然あるべきこととされ、その弊害につ
いて、あまり省りみられることがないようです。しかし、好き嫌いの感情の「真実を歪める」という性格を考えたとき、だれにでもあるのだから…、といった安易な気持ちになってはいられないのです。