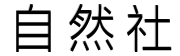今月の言葉 > 「標語解説書」から > 平成16年版15日
国を支える気概があってこそ
健全な社会を築ける
国を支えるなどと言うと、大言壮語(自分にふさわしくない意気盛んな言葉)を吐くとか、右寄りの考えに傾いて、と言われそうですが、そんな大げさなものではありません。
国は組織と法令とそれぞれの部署を担う人によって動いており、国民一人ひとりは直接国の仕事に携わっていなくても、自分の立場に応じて社会を支え、国を動かす役割を担っています。このことを心に置いているか否かで、自分の生き方が違ってくるのではないか、と思うのです。
国を…、となるとあまりに対象が大きくて実感がわきにくいかもしれませんが、例えば学校の部活でも、みんなについて楽しくやろうとしている人と、何とか部をもり立てて、部活を通してみんなが充実感や達成感を得られるようにしたい、と思っている
人とでは、日ごろの活動の仕方が違っているはずです。そして、そういう部員がいるかいないかで、部活の実力が上下するだけではなく、部室に入ってくる時の表情まで変わってくるのではないでしょうか。
ところがみんなが自分のやり方や意見にこだわって、それぞれに好きなことばかりやっているようだと、だんだん自分の都合を先に立てるようになって、お互いが本気で意見を言い合ったり、力一杯練習に取り組んだりする雰囲気が失われていきます。これでは出席数が減っていってしまうかもしれません。
国と部活では規模が違いすぎますが、学校でも、会社でも、色々な団体でも、みんなのこと、組織全体のことを心から思って仕事や活動に取り組む人がいなければ、その組織が生き生きしてくることはないでしょう。
人間は自分のことを第一に考えたい気持ちを強く持っていますが、その気持ちだけでは幸せにはなれないことを、人との交流を通して知ってきました。
そして、周りの人と一緒に味わう幸せがより大きなものであることを、色々な経験を積んで深く知ってきました。
「国を支える気概」というと大きすぎるように思えますが、自分の都合を一時置いて周りの人のためを思う気持ちは、国のような大きな組織を支えることに通じているのです。