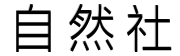今月の言葉 > 「標語解説書」から > 平成14年版11日
分かっているという思いが
心の成長を止めている
「分かる」ということには無限の段階がありますが、私たちは物事の表面を知っただけで、もうそのことは分かっている、と思ってしまうことがあるものです。
しかし、物事が本当に分かるということは、それを体験して中身を知り、自分の考えと行動に体験から得た知識がきちんと組み込まれてはじめてそう言えるのであって、さらに言えば、そのことに関わる人の気持ちを知ってこそ、自分の心の成長に役立っていくことになるのではないでしょうか。
未知の物事にふれたり書物を読んだりして、これまで知らなかったことを知ったとしても、そのことが「分かる」ということからすれば、その入口に立
ったに過ぎません。
それなのに「分かっている」かのような思いを持ったとすると、それは自己満足に陥ってしまっているということになります。
人間は様々な体験や思索を積んで、ものの考え方をしっかり持ち、これを通して自分の内面を知っていくことから周りの人の心も分かるようになって、自分の働きを伸ばしていきます。
ですから「分かっている」という思いになるということは、物事を深く知って、それを身に付け、自分の成長に役立てていこうという、大事な心の働きを見失っている姿でもあるのです。
物事の表面だけをとらえて分かったと思ってもそれはごく僅かなことで、その奥にもっと大事なことがたくさん隠れているものです。
その大事なことに気付いていくこと、あるいは大事なことを探り当てようと努めることが、心の成長につながっていくのです。
しかし、分かっているという「我」を立てた思いからは、そういう探求心や求道心は生まれてきません。真摯に物事を見つめて大事な意味を知ろうという謙虚な姿勢や、これを周りと自分のために生かしていこうという積極的な気持ちは、「分かっている」という偉そうな思いとは同時に存在しえないのです。
心の成長を望むのなら、自分の知らないことはたくさんあると知って、物事と自分のありのままの姿を見ていくことです。成長していくための材料は無限にあるのです。