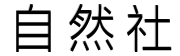今月の言葉 > 自然誌 文章から > 令和 3年 1月号 真理の展望
人を鏡と見る人ぞ人
橋本のり子
昨年の夏、長男が本宮出仕に行く前日に我が家に来て、庭の木の剪定(せんてい)をしてくれました。その時庭の向こう側の奥さんが出てこられたようで、長男と何か話をしている様子でした。しばらく経(た)って長男は作業を終えて家に入ってくるなり、「お母さん、老人ホームに入ったと思われてたよ」と言いました。ホームに入っている母親のためにわざわざ剪定に来て偉いね、と言われたそうなのです。
「えーっ何でー?」私は驚きました。そして恥ずかしいことですが、とても腹が立ちました。私は手術をしてから体が思うように動かず、もどかしい思いをすることもありますが、立場を全うするため毎日精一杯働いています。そんな私のことを、ホームに入ってのんびり過ごしていると思われていたことが
心外で、私のプライドが傷つけられたように感じたのでした。
それに私は洗濯物を干したり庭作業をしたりしていますから、少し様子を見てくだされば、私が家に住んでいることは分かりそうなものです。どうしてそれが分からないのかしら、という強い不満もありました。
さらに長男の話を聞くと、私が手術をした後に「町内会費は払うが回覧板は回さないでほしい」と頼んだことから、私がホームに入ったという噂(うわさ)になっていたということが分かりました。きっとその噂を信じて、私はもう家にいないと思い込んでおられたのでしょう。長男はその奥さんに、私はまだ家に住んでいることを伝えたとのことでした。
さてそれから小一時間経った頃、その奥さんが「マドレーヌを焼きましたから、召し上がってください」と持って来られました。そして「お元気で安心しました」と言って、さっと帰られました。庭は背中合わせですが玄関は反対向きとなることで、ぐる
っと回って来なければなりません。きっと誤解をして悪かったと思われたのでしょう。私の方がすっかり恐縮してしまいました。
その時私は、これは鏡だ、と気付きました。この奥さんの姿は正しく自分の姿だと思ったのです。私も物事をこうだと思い込んで決めつけてしまうことがしばしばあります。何かをするとき「普通こうするものだろう」と以前の経験だけで判断して間違ったことをしてしまったり、この人は昔こうだったから今もそうに違いないと決めつけて実は全然違っていたり、ということが何度もあります。
その都度、思い込みはよくない、と反省はしますが、その癖はまだまだ強くあります。きっと、私のこの癖のために、周りの人たちは嫌な思いをしたり迷惑を被ったりしていることでしょう。そのような私の姿を鏡として見せてくださったのだと痛感しました。
その奥さんはその後も、「スイートポテトです」とか「クッキーです」と手作りのお菓子を持ってきてくださいます。きっと「橋本さん、傷つけてごめ
んなさいね」のお気持ちなのでしょうが、私の方が申し訳なくて、洗濯物を干す時いつもお隣を向いて「ごめんなさい」とお詫(わ)びしています。
○
「人を見て人と思ふは常の人 人を鏡と見る人ぞ人」という教祖様の御歌があります。私たちの多くは人の姿を見て他人のことだと思ってしまいますが、人の姿を自分の鏡だと受け止める人こそ本当の人だ、という教えの歌です。ところが私たちはまだまだ本当の人にはなっていないようです。
神訓で「人は鏡」と教えていただいているにもかかわらず、これを心から信じ、日頃の生活で真剣に取り組んでいる人は少ないのではないでしょうか。人の姿を見てそれが自分の気に入らないと、すぐに批判の思いが湧いて不満が込み上げてくる人の方が多いと思います。このような思いをするだけで終わってしまったとき、自分の向上には全くならず、ただ批判する癖と不満を思う癖が一層積まれていくことになります。
だいぶ以前、高野山奥の院で座行(ざぎょう)を
しています時、教祖様から鏡ということについて教えていただいたことがあります。「自分一人で自分のありのままを知ることは至難なことだ。他があるというこの神業は何か。それは自分を知っていくための恵みである」とおっしゃったのです。
そう言われてみるとそうだなあ、としみじみ思いました。幽界からこの世の中に人間として生まれさせていただいたのは、少しでも自分の心の誤りを消して罪障を浄(きよ)め、再び幽界に戻っていくためです。それには、自分がどんな人間であるか、生活の中で気付いていかなければなりません。
幽界のように、一人きりでもじっとしていたいと思えばいくらでもじっとしていられる所で、自分というものを分かろうとすることはなかなか難しいことです。この世に生まれてきて他人とのやりとりをする中で、相対する人を鏡として自分の姿に気付いていけるのです。自分の「業」を浄めるために他があるという、尊い神業の恵みの中に生かしていただいているということなのです。
そして教祖様はある時こうもおっしゃいました。
「『世は鏡 人は鏡 子は鏡』という通り、相手の中に自分を見ると必ず自分がある。だから心の基本として、困った者を相手としていたら必ずその中に自分があるんだ、という見方が必要だ。他を排斥したり批判したりしていては何も得られない。せっかくの恵み、他という神業を生かすことができなくなる。それでは変われないのだ」と、繰り返し教祖様がおっしゃったのです。
世間ではよく「反面教師」という言葉が使われます。困ったことをする人を見て悪い見本だと思い、「自分はあのようには絶対しないぞ」と思うことです。そのとき、あの人は人間が出来ていないからあんな事をするが、自分はきちんとした人間だからしない、という上から目線で見ています。形の上からだけ見ればそうかもしれません。しかし心の姿を見るとき、全く同様な自分がいるはずです。
車の運転に限れば自分はあんな乱暴な運転はしないという人でも、周囲の人の気持ちを考えず自分の都合でごり押しをすることがあるかもしれません。
形は違っても、自分のしたいことを強引に押し通すという心癖は同じです。人の嫌な姿を見たとき、自分も同様なことがきっとあるに違いない、と反省する生き方、それが「鏡と見る人ぞ人」なのです。
○
昨年「人間たらしめる生き方を貫き向上の一年としよう」という信仰実行目標を頂きました。これは、人間だけに頂いている意志の力を発揮して向上していこう、つまり自分はどのように生きていくかをはっきり決めてそれを貫き意義ある一年にしよう、という意味です。二月の節分まであと一箇月余りこの目標が続きますので、初心に返って取り組んでください。
そして「人を鏡と見る人ぞ人」は、人を鏡と見てこそ人間なのだ、という意味で、これも本来人間のあるべき生き方を教えていただいています。人間らしい人間を目指すことを目標に掲げている今こそ、今まで疎(おろそ)かにしていた「鏡」の大切さに目覚め、「人を鏡と見る人ぞ人」を心に刻んでいただきたいと思います。