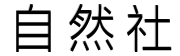今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成31年 1月号 真理の展望
心と行いを一致させて生きる
橋本のり子
私が結婚してしばらく経(た)った時、舅の( しゅうと )初代教長橋本郷見先生が「何事も心と行いを一致してこそ、実りある結果が出るのだよ」とおっしゃいました。私はそれをお聞きした時、大変おこがましいことですが「思いもしない事を体がするはずはないのだから、心と行いが一致しているのは当然じゃないかしら。どうしてわざわざそんなことをおっしゃるのだろう」と思いました。(もちろん口には出しませんでしたが)
今は教長様のお気持ちがよく分かります。私のしていることを黙ってご覧になっていて、「せっかく苦労してやっているのに、やったことにならないからもったいない」と思われて敢(あ)えておっしゃってくださったのです。
例えば、晩ご飯のおかずの魚を焼くときのことで
す。橋本家では七輪で焼いていましたので、もちろん私も七輪で焼くのですが、仕方なくそうしていました。形の上では確かにしてはいるのですが、心の中では「七輪は火を熾(おこ)すのが面倒くさいし、煙がたくさん出て頭まで臭くなるから嫌だ。フライパンで焼いた方がいいのに」と思いながらしていました。私の心は行いと全く別の方向を向いていたのです。
魚は七輪で焼くと決められているのであれば、それをそのまま受け入れて焼いていくことが望ましいのですが、私はそう簡単に受け入れる心にはなれませんでした。そこで初めのうちは魚もうまく焼けず、黒く焦げたり崩れたりすることがありました。しかし面倒だと思いつつもそれを仕事として重ねていくうちに、焦げないように崩れないように、そして家族を思う心となって美(お)味(い)しくなるようにと、魚を焼くという行いに従った心に変わったのです。そして当然のことですが、魚の焼き方も知らぬ間にうまくなっていきました。このことを通して、自分のすることについては心と行いを一致させ
てすることが何よりのコツである、と分かったのです。
「心と行いを一致させて生きる」ということは、自然(さながら)にして生きるということで、心と体がズレない、ストレスのない姿で生きることです。これは自分の立場を全うして生きるための、質を高めていけるという大切なことの元になるのです。
教長様は一緒に生活をしていて、日頃の私の姿をご覧になっているからこそのアドバイスを下さったのです。
○
「心と行いを一致させる」ということは、自分の立場を全うして、質を高めていけるという大切な問題です。
動物にはこのような課題はありません。例えばサーカスの曲芸をする動物は、鞭(むち)で脅されたり餌(えさ)で褒美を与えられたりしながら芸を仕込まれます。そして覚え込んだ芸を披露するという単純なものです。
しかし人間は、自分の心と行いを自分の意志で決める自由を持っています。物事を行うについても、それを行うこともできますし、頑として拒絶することもできます。また同じ行うにしても、進んですることもできますし、嫌だなあと不満を一杯抱きながら行うこともできます。このように、心と行いを全て自分の意志で決めて行うことができるのが、人間が人間である尊さです。
ところがこの尊さを知らず、どんな心でするかを自分で決めて行うということを知らないと、ある感情が湧いたときにその感情に流されて、自分自身が振り回されてしまうことになります。何かを行っていても、その行っていることと全くかけ離れた思いを持ち続け、心と行いがバラバラな状態で行動することになってしまうのです。
○
「心と行いを一致させる」ということは、行ったことがよりよい結果を生んでいくことになるのです。そしてそればかりではありません。
人間は霊魂を浄め向上させていくためにこの世に
生きています。霊魂を浄める道は色々ありますが、その中でとても大切な柱となるものは、自分の仕事に誠を尽くすことです。ここで仕事というのは、報酬が得られるものだけではありません。誰かのため、あるいはみんなのためにお役に立つ行いは、みんな大切な仕事なのです。
自然社では勤労奉仕のことを「みそぎ」と言っていますが、「みそぎ」を始める時の誓いの言葉に「いかなることも進んで喜んで行います」という一節があります。進んで喜んで行うことがまさしく心と行いが一致している状態であり、霊魂の浄めを頂くことになるのです。
つまり、心と行いを一致させて物事を行うことは、その仕事が実りある結果をもたらすと同時に、霊魂の浄めという実りをも頂けることになるのです。もしも、仕事を仕方なしにしていたら、全く霊魂の浄めとはなりません。「やったことがやったことにならない」とはこのことで、教長様はこの大切なことを私に教えてくださっていたのです。
○
心と行いがバラバラになっている例として、不満に捉われている場合を上げましたが、別のケースもあります。私はせっかちで、以前は歩いているときに時々躓くことがありました。躓く(つまず )のは、今現実に歩いていることから心が離れて、先のことに捉われるという急ぎ心が原因です。
そんな私ですが、三年前に背骨の手術をした後、歩いたり動いたりする際に自分の心と動きがピッタリと一致しているのを感じました。意識しないと体を動かすことができないほど体が硬くまた重い状態でしたので、例えば食卓から冷蔵庫に行くだけでも大変なことでした。冷蔵庫に物を摂(と)りに行きますと意識して、まずテーブルに手をついてしっかり支えた上で、右足で立ち上がるぞと言い聞かせて力を込めてようやく立ち上がり、物に掴(つか)まりながら次は左足を出すと意識して一歩進むという具合でした。やっとのことで冷蔵庫にたどり着いた時は、歩けたことに心から感謝の思いが湧いてきました。そして当然のことですが、その頃は転ぶことはありませんでした。
ところが、体が徐々に回復していくうちに、自分の手元や足元のことよりも先のことを考えてしまう癖が出てきました。そしてどうかすると転びそうになります。お医者さんから、私の今の体は転んだら大事になってしまうから絶対に転んではいけない、と釘(くぎ)を刺されているにもかかわらず、足元のことをつい忘れて心が先のことに動き出してしまいます。このように自分の思いに捉われてしまうことが、心と行いが離れて転びそうになったことの原因です。
神訓で「怒る急ぐ憂へる悲しむは物事を崩す」と教えていただいていますが、今自分が行っている手元のことから心がすっかり離れて散漫となり、心と行いがバラバラになっている状態では、物事が崩れていくのは当然でしょう。
今目の前のことに心を込めて、喜びの心を持って一つ一つに誠を尽くすことの積み重ねをして、自分の立場を全うし、人生を実りあるものにしていくことを願っています。