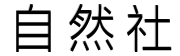今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成30年 8月号 真理の展望
精進は無限である
橋本のり子
私たちはこの世に生まれてきて、人間として霊魂を浄(きよ)め向上するために精進をしています。すっかり出来上がって向上する余地は無い、という人は一人もいません。私たちとは全くかけ離れているように思う教祖様さえも、この世で懸命に修行をされ、さらに亡くなられた後も幽界での御修行を積まれて神界へと進んで行かれました。それと比べること自体おこがましいことですが、私たちが努力して何か一つのことを悟ったり身に付けたりしたとしても、それで自分がそこそこ出来た人間になったと考えるとしたら、思い上がりとしか言いようがありません。
もちろん今日まで努力して積んだものは、自分の心境や力として残っています。零点の人もいないし百点の人もいないのが人間です。
例えば「一切は恵みである」ということについてどの程度確信しているかは人それぞれで、自然社の信仰をしている方なら、全く信じられないという人はいないでしょうが、かと言って、何が起きてもいつもそれを恵みと感じて感謝の気持ちばかり湧いてくる、という人もいないでしょう。
想像してみますに、教祖様は色々な事に出会う度に、それを恵みと受け止めて神様に感謝しておられただろうと思います。また初代教長橋本鄕(さと)見(み)先生も「何事も喜びて神(かん)業(わざ)のままに生くるのが人生である」と常々語っておられて、物事にあたふたと一喜一憂することはほとんどなく、何事についても神業として頂いておられました。
その御心境と比べますとまだまだ、まだまだ至らない私たちですので、少しずつでもその信念を深めていくことが大切です。
まず初めに、「一切は恵み」と教えていただいていることがどれほど有り難いことであるかを、よくよく心に刻んでおきましょう。もし自然社の教えを
知らずにいたら、自分の期待に外れたことが起きたとき、すぐ「なんで」「どうして」「もう駄目だ」というような「怒る急ぐ憂(うれ)へる悲しむ」の思いが湧いてきて、それに捉(とら)われてしまうことでしょう。その思いは物事を崩す働きがありますので、一層不具合を生むことになります。
この教えを頂いているお陰で、「よく分からないけれど、これでいいのだ」とそれなりに受け入れることができます。そこからまた一歩進んで、「私にとってこれが一番いいのだ」と心からの納得へと進んでいけます。
もちろん、私たち凡人はなかなかこの切り替えができないのですが、それを少しでも進めていくことを目指す必要があります。そのためには、体験を積み重ねてくことしかありません。
例えば、子供が志望大学の受験に失敗したとします。あれほど頑張っていたのにと、子供が不(ふ)憫(びん)で親としても現実をなかなか受け入れられません。しかし親ががっかりしていたのでは、子供を一層落ち込ませてしまいます。そこでどこに恵
みがあるかを考えることになるでしょう。
そう言えばうちの子は高校生まで挫折したことがなく、世の中のことを甘く見ていたし、何かと偉そうな態度が増えていた。今回の失敗が無ければ、いよいよ傲慢になって、社会に出てから困ることになっただろう。それに自分の実力の足りなさに気が付いて、日頃からコツコツ努力するように変わっていくきっかけだ。・・・・・・・・そこまで考えが至れば、本人にとってこれが良かったと受け入れていけます。
ただし、親は心の切り替えができても、本人はそう簡単に切り替えはできないかもしれません。それは、他人が見る目で自分を見ることが難しいからです。傲慢であることも日頃怠けていたこともほとんど気が付いていないので、なんであんな解答をしてしまったのかと後悔したり、もう自分は駄目だと落ち込んでしまうかもしれません。何年も経(た)って後、社会人になって色々な苦労をする中で、自分が受験に失敗したことは自分にとって良いことだった、恵みだったと分かるかもしれません。その時に
「一切は恵み」ということの信念が一つ培われます。
このように大きな事でも些(さ)細(さい)な事でも、自分が望んでいない出来事が起きたときに、一旦は心が動揺するでしょうが、そこから「これでいい」と受け止め、さらに「これがいい」と心から受け入れるという切り替えを一回でも多くしていくことが大切で、その積み重ねがやがて「一切は恵みである」ことへの信念へと進んでいくのです。
○
自然社で世の中の理法を教えていただいたから、これで世の中のことが分かった、悟ったと考えるのは浅はかで、それはただ出発点に立ったというだけのことです。そこから一つまた一つと体験をすることで、少しずつ悟りを深めていくのが人生の修行なのです。
もう一つ、鏡ということで説明してみましょう。
「世は鏡人は鏡子は鏡」と神訓で教えていただき、私たちは「鏡」ということを少しは意識していま
す。しかし、この神訓は全く真理だ、と心の底から確信を持って、日々の生活で大いに生かしている人はあまりいないのではないでしょうか。
もちろん、周囲のことを鏡だと感じた体験は誰でも少しはあるでしょう。例えば、強情を張って言うことを聞かない子供に対して腹を立てていて、ふと自分の子供時代を思い出して、親から「おまえは本当に強情だ」と叱られた自分だったと気付き、自分は親に苦労を掛けたのだと反省して、本当に子供は自分の鏡だな、としみじみ感じることもあるでしょう。
しかし、これで自分はこの神訓が分かった、悟ったといい気になるのは大きな間違いで、やっとこの理法の一端を垣(かい)間(ま)見ることができた、というところです。もし本当に悟りきることができたなら、周囲の言動を見て腹を立てるというようなことはほとんど無くなり、何を見ても即、自分自身をじっくり省みるという暮らしぶりに変わるはずです。
教祖様は「人を見て人と思うは常の人 人を鏡と
見る人ぞ人」と詠まれました。おそらく教祖様は、人の姿を見て腹を立てるということは少なく、また上から目線で人を見て軽蔑することもなく、何を見ても自分の精進の糧としようとして生きておられたと思います。文字どおり周囲を鏡として受け止めておられたと思うのです。
それと比べれば、「鏡」についての私たちの悟りはとても浅いとしか言えません。せっかく頂いているこの神訓を、もっと日頃の生活で生かしていきたいものです。
○
何か一つ体験をして、それでもう教えが分かってしまったように思っていないでしょうか。そんな思いになると、精進への真剣な気持ちが弱まって前進していかなくなり、偉そうな思いだけが増えていきます。
人間の精進は無限です。一回でも多く体験を重ね、信念を少しでも深くしていかなければなりません。「一切は恵みである」ことを本当に悟っていこうとか、「人は鏡」ということを確信しようとか、あ
るいはどんなことでもいいですから、自分なりの目標をはっきり定めて、生活の中での体験を積み重ねていただきたいと思います。