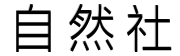今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成30年 1月号 真理の展望
浄心・忍耐・反省
橋本のり子
初代教長橋本鄕(さと)見(み)先生は、色紙に「浄心・忍耐・反省」の三つの言葉を書かれて、本庁の「みおしえ」をされる部屋の壁に掛けておられました。このことは、鎮魂のための三要素として教長様が日頃これを肝に銘じ、実践に励んでおられたことを物語っています(この場合の鎮魂とは、自分の魂を鎮めて穏やかにするという意味です)。私がかつて読んだ本にもちょうどこの三つの言葉について書かれているところがあり、霊魂を鎮めるために是非必要なことだと説明されていました。霊魂は人間の本体です。その本体が安定せずに彷(さま)徨(よ)っていたのでは、生活を確立して揺るぎない幸福を築き上げることはできません。ですから幸福を目指すものは皆、この「浄心・忍耐・反省」と取り組まなければならないのです。
それは今生のことだけを言っているのではありません。寿命が来てあの世に行ったときに、この世で手に入れた物や名誉などは一切捨てることになり、ただどのような霊魂であるかだけが問われます。生まれた時よりもより良き霊魂となってあの世に行くことが、今生の人生の意義なのですから、「浄心・忍耐・反省」は人生修行の要と言えるでしょう。
そこで、この三つの言葉の意味をここに説明しようと思います。
浄 心
私たちは毎日色々な思いをしながら生きています。思いは形がありませんので、思いが治まったら何も残らないと考えがちですが、それが大きな誤りです。それについては橋本鄕見著作集第二巻の「思いは残っている」に詳しく書かれていますのでここでは省きますが、残ると分かっている以上、なるべく良き思いを重ねることを目指し、また悪(あ)しき思いは出さないに越したことはありません。
しかし、思いは癖のままに出てきますので、出さないようにすることはできません。そこで不満や心
配などという要らぬ思いを出したら、それに気が付いて素直にお詫(わ)びをすることが大切です。その謙虚な真心に対して神様が心を浄(きよ)めてくださいます。
また自分の心を穢(けが)すような思いをしていても、それに気付かないことは多くありますが、それを浄めていただく道はあります。他のために一心に働くことは、知らず知らずに穢してしまった心を浄めていただくことになります。ですから自然社では「みそぎ」として勤労奉仕や金銭奉仕を行っています。
また、謙虚な気持ちになって神前に額(ぬか)ずき、「至らぬ私を浄めてください」と真剣に祈り、これを重ねていくことで神様の浄めを頂けます。特に、意を決して早起きをし、教堂の浄心の行に参列することは、神様の浄めを強く頂く事になるのです。
このように「浄心」を意識しそれを願って暮らすことは、私たち信仰者がまず目指すべき道なのです。
忍 耐
忍耐の説明では、まず我慢との違いを述べる必要があります。忍耐を辞書で調べると「我慢すること」と書かれていて、同じ意味というのが一般的な解釈ですが、教長様はそれを使い分けておられました。心では納得していないのに、無理やり自分の気持ちを抑えつけることが我慢で、一方自分が今それを頂くべきときであると納得し、現実を受け入れた上でそれに耐えていくことが忍耐です。形の上では同じように見えるのですが、心の中身は全く異なっていて、我慢ではなく忍耐をするようにと教えてくださっています。
我慢をしているとストレスが溜(た)まっていきます。やがて耐えきれなくなって爆発することもあるでしょう。たとえ爆発しなくても、不満という自分の心を穢す思いが積み重なりますので、それは必ず物事を崩す力となり、幸福を生み出すことを邪魔していくことになります。
一方忍耐は、現実をそのまま受け入れていますからストレスは溜まりません。忍耐は何日間も、ひい
ては何年間も続けていくことができます。
例えば、誰かに誤解をされたとします。弁解をして誤解を解くことができれば問題ありませんが、弁解をすればするほど言い訳となって、一層誤解が深まるときもあります。そのようなときは良しと受け入れ、いつか分かってくれる時が来ると信じて待つことで、それが忍耐に当たります。
この場合「人は鏡」だと悟ることが元になります。日頃の自分の言動の中に不信感を抱かせるような不誠実な点があったのかもしれない、あるいは自分も人に対して自分の色眼鏡で見て誤解することもあるだろう、というように、人の姿を通して自分の問題点を知る機会にすれば、自分が誤解されたのは当然のことだと受け止めることができて、我慢ではなく忍耐ができるのです。
もっと広く言えば、一切が神業であり恵みであるということが分かれば、現実をそのまま受け入れることができます。そして自分は自分のやるべき事を尽くしていれば、ふさわしい時にふさわしい変化が現れると信じて、淡々と生きて行くことができるの
です。
反 省
本誌の表紙裏に書かれていますように、自分をありのままに知っていくことが人間生活の一番の目的です。そして何かの出来事が起きて心癖を出している時に、これが自分の姿だとはっきり気付くことができれば、不要な癖は神様が少しずつ浄めてくださいます。
しかし、その場では自分の癖に全く気付けずに過ぎていることの方が多いでしょう。また気付いたとしても、その状況に捉(とら)われる思いが邪魔をして、ありのままの自分には気付けないことが多いと思います。そこで、後から振り返る反省ということがとても大切なのです。
反省について教長様から「紙芝居のように場面を絵にしてみなさい」と言われたことがあります。相手がいるなら相手を出しなさい、場面があるなら場面を出しなさい。そうやって見ていくうちに、あっこれだ、と単純に素直に自分の誤りに気が付いて、それを認める一瞬がある、それが反省だ、とおっし
ゃいました。
つまり第三者の立場に立って自分を客観することが反省なのです。ですから後悔とは全く違います。私たちは過去の嫌な出来事を振り返る時に、反省ではなくつい後悔をしてしまいます。後悔は自分にとらわれきったままで過去を蒸し返すことですから、自分の気持ちを暗くするばかりで何の役にも立ちません。本当の反省をすれば、自分の誤りをはっきり悟ることになりますから、必ず改まっていきます。気持ちが明るくなり、前向きの気持ちになれるのです。
○
「浄心・忍耐・反省」は信仰者として霊魂を鎮めていくための要であり、神の救いを頂くための道筋であります。教長様が生涯を懸けて取り組まれたこの三つの精進を、私たちも自分自身のために精進の大きな柱として頂いて、日々の暮らしの中で実践をしていきたいと思うのです。