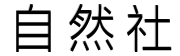今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成17年11月号 真理の展望
世界に一つだけの花
森山 勝
槇原敬之が作詞・作曲しSMAPが歌って大ヒットした「世界に一つだけの花」に
…そうさ僕らは 世界に一つだけの花
一人一人違う種を持つ
その花を咲かせることだけに 一生懸命になればいい…
というフレーズがあります。
◎
歌はその時代の社会を反映して、人々の心を癒したり慰めたり、あるいは勇気づけたりしてくれます。この歌も、私という個人は世界にただ一人の存在であって、この自分も周りのみんなも尊い存在だと、花に託してこの世に生を受けた意義を謳歌しています。
この歌が世に出た当時の我が国は豊かで明るく見える一方で、経済は伸び悩み、年間の自殺者数が三
万人を超える不安な時代でありました。この数は交通事故の犠牲者の三倍にものぼる深刻な問題で、失業者の増加と共に社会に暗い影を落としました。
先行きの見えない不況のもとで働き盛りの人たちが自ら死を選ぶ、それだけ悩みは大きかったに違いないのでしょうが、自分の命を軽く考え粗末にしていく人が多い、そんな社会風潮に悩める中年層の応援歌となりました。
俗に「命あっての物種」と言いますが、生きていればこそ花も実もあるのであって、どのように苦しい立場に立とうとも悲しいことが起ころうとも、それはいつまでも続くものではなく、やはり辛くとも生きていてこそ、失地挽回の機会も得られます。
この明るい元気の出る歌によって慰められ、気持ちの転換を図って、生きる意欲を取り戻したり、行き詰まりを打開した人も大いにあったのではないでしょうか。
◎
考えてみれば、この世に自分と同じ存在は二人となく、私という人間はこの宇宙でただ一人の存在だ
からこそ生きていることに価値があるのであり、より良く生きようと志すことは何より尊いことであると言えます。
自分の何が偉いというのではなく、この世にただ一人の自分として生を頂いていること自体が尊く、「有り難い」ことなのです。ところが私たちはそうした本当にかけがえのない自分として自身を見たり、お互いを人間同士として尊びあう気持ちで見ているでしょうか。
むしろ人は二人以上集まると、無意識のうちに他と自分を比べて、他より優位な場合は相手を馬鹿にしたり、逆に人より劣っていると思うと卑屈になったりと、そんな生き方が私たちの身に付いているように思えます。
現代では、自分の命を軽く考えて粗末にしてしまうくらいですから、他人のこともさほど重く受け止められないことになっているようです。
しかし、人は必ずしも頭がよいとか、切れるとかというだけで、必要とされたり尊ばれるのではありません。周囲から少し「ぬけている」と思われると
ころがあっても、その人がいるだけでその場が和む人もいます。そんな人が急にいなくなると、その人の存在価値があらためて分かったりするものです。
この世に生まれ出たということは、私たち一人ひとりが、他とは代えられない、かけがえのない貴重な存在であるということを、もっと自覚していく必要があります。
そうした意味から言っても、自分自身を大切にすると同時に、他の人を尊ぶ心を磨き出すことが重要になります。
◎
私たち人間は、それぞれが世界で唯一人の存在で、尊いことに違いないのですが、何も努力せずにただ漫然と生きていってよいということではありません。私たちはこの世に完成した状態で生まれ出たのではなく、まだ原石とでもいうべき状態にあるわけですから、やはり磨かなければ価値は少なく、輝きはしないのです。
人間は、限りある人生とは知っていても、目先の
欲につられて、好き勝手な生き方をしがちです。しかし寿命を頂いてこの世に生きるということには本来使命と目的が与えられています。
このことを毎月、本誌の表紙の裏面に「人間の本体は霊魂である」と題して載せられている中に「霊魂がこの人間自覚への精進にひたむきになり、人間とは何かを知っていくことこそが、人間生活の真の意義であります」と記されています。
人は、幼時は慈しみ育まれる中で躾けられ、学校教育で知識を学び、社会に出てからも、仕事を通して、あるいは周りの人との交流から、人としてこの世で生きる術を身につけていかなければならないのであって、人の一生は、自分の心をありのままに知って、心を磨く修行の場になっています。
人に、心を磨くという意志が生じなければ、神はさまざまな悩みや苦痛という形をとって人間各自に現されます。そしてこれは否応なく、すべての人に平等に課せられています。
「神訓」第十一条に「ひとはかみの表現であるひとより尊いものはないことを知れ」と、神と人間との
関係と人間の立場について説かれています。
人間みずからが、自分はこの世に現れたものに、形と方向をつける立場にいるという、自分の立場とその能力を自覚し、さらにそれを高めていく精進こそが人間生活であって、それが人生の目的であるということです。
もしも人間の欲望をほったらかしにしておいたら、物欲も金銭欲も出世欲も無制限に加速していくことでしょう。そのような性質を持っているのが私たちです。
そこで欲望だけに限らず、心癖を自覚して心のあり方を自ずからに正していく「浄心」の修行にしっかり励んでいかねばなりません。
目指すべき一つを言えば、我が国では古来より「正直できれいな心」「裏表のない心」といった心のあり方が求められてきました。
さらには「素直で争いごとを好まない」「黙々と努力する」「約束を守る」といった「心の清潔さ」に大きな価値を見出してきました。
これを「清き明き心」、そして「直き心」と呼ん
できました。このような心のあり方に重要な価値を置く生き方を、私たちの先祖は何よりも尊んできたのです。そして、この生き方こそ今も私たちが幸せな人生を築くに当たって最も大切なものです。
「正直者が馬鹿を見る」と言う一方で、「正直の頭に神宿る」と、神のご加護を信じてきた日本人です。
◎
歌に込められた作詞者の願いは知りませんが、「その花を咲かせることに一生懸命になればいい…」という言葉に、清き明き、そして直き心を大切に思い、そんな人になろうと努力してきた日本人の伝統を思います。
プレッシャーのため一度はくじけたと聞くこの作者が、そこから立ち直り、これを信条に多くの人に「明るさ」への道筋を提示しました。
それを思うと、人間自覚への道は苦痛があってこそ、そしてそれを乗り越えるため、素直な明るい心で「黙々と努力する」ことだと、自然社の教えの深い意味をあらためて感じるのです。