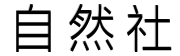今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成17年 8月号 特集 自然社の教え
「もったいない」という生き方
森山 勝
マータイ女史
昨年のノーベル平和賞は、ケニア共和国の副環境相ワンガリ・マータイ博士が受賞しました。環境保護運動や民主化への取り組みが評価されたもので、環境分野の活動でノーベル平和賞受賞は初めてのことでした。
マータイさんは、森林が伐採されて薪を集められず、子供の食事も作れない農村女性の姿に胸を痛め、自宅の裏庭に7本の木を植えました。これをきっかけに「グリーンベルト運動」を創設。今ではアフリカの20の国で約10万人が参加し、植樹した苗木は三千万本に上ります。
環境保護だけでなく民主化や女性の地位向上にも尽力。このため独裁的な前政権に弾圧されましたが、前の政権が倒れた2002年に国会議員に当選し、翌年環境副大臣に就任。不屈の精神と、誰とでも
分け隔てなく接する人柄で国民の大きな支持を得ています。
マータイさんは今年3月ニューヨークの国連本部で演説し、日本語の「もったいない」を、全世界の環境問題のキャンペーンの合言葉にしようと提案し「さァ皆さん言ってみてください。モッタイナイ、モッタイナイ」とリードすると、会場に「モッタイナイ、モッタイナイ」の合唱が広がりました。
4つのRを
マータイさんは来日した時「もったいない」という言葉を知って深く感じ、これを世界に広めることを決意しました。
「もったいない」は英語に訳せない言葉だそうで、日本政府が①リデュース(ごみの減量)②リユース(再使用)③リサイクル(再利用)の3R運動に取り組んでいることを紹介し、「日本ではこれらを『もったいない』の一言で表します」と話して、この3Rに④リペア(修繕する)を加えた4Rで「もったいない運動としよう」と提唱したのでした。
原油や石炭、鉄鉱石や化学原料は、世界的な不足
で値上がりし、紛争が起こりかけています。そこで「4R運動により持続可能な開発を実現し、限りある資源を有効利用して、公平に分配すれば資源をめぐる紛争は避けられる」と訴えました。
21世紀は資源の世紀と言われていますが、平和的にこれを解決しようと「もったいない運動」を推し進めているのです。世界の環境問題を解消する言葉だと外国の人から指摘されて、あらためて日本の精神文化を見直し、日本の素晴らしさを知りました。
「もったいない」の「もったい」は、漢字で「勿体」「物体」と書き、そのものの「本来の姿」や「使命」「価値」を指します。
国語辞典に「もったいない」の意味は①畏れ多い②非常にありがたい③むやみに費やすのが惜しい等と出ていますが、一言では言い表せない奥深い言葉だと感じます。
本来の姿
温暖化など様々な環境問題が差し迫っていますが、危機を間近にして個々人の生き方は変わったと言
えるでしょうか。物が十分にない時だけ物の節約を唱える、そんな目先のことに終わっているように思えます。
「信仰とは何か」を考えるに当たり「もったいない」をキーワードにしてみましょう。
幸せに暮らすには、自分にとらわれた心を離れ、社会の多くの人々と共に救われ、共に幸せになっていこうとする心が大切で、これは環境保護にも通じる心です。
私たちの周りにある一切の物は、すべて生命あるものであり神からの恵みです。それを感じて、感謝して使う生き方は立派な信仰であり、この生き方をしていけば身の回りの物に対する思いが変わっていくことでしょう。
それぞれの物が持っている本来の価値を十分に生かして使い切ること、そうした心で物を使っていけば、物の働きが増すなど違いが生じてきます。
生活そのものが
「物を大切にする」ことは、無駄なく物を生かし、捨てるものを少なくしていきます。物を大事にする
ことを通して、何でも好き放題にする思い上がった気持ちや怠け心に気付くことができたら、心は一層軽くなります。
この心を深めようと努めることは、他を思いやる気持ちを深めることであり、幸せに近づくことになります。
「物を大切にする」ということは、口で唱えるだけでなく、実際にそのような暮らし方をしてこそ環境破壊の防止になります。
自然社の信仰もこれと同じで、教理を知ったり、特別な修養をするのではなく、この教えによって、「人間として本然の生き方である、世に現れた一切のものが一つに和して、平和で幸福な生活を営むこと」を目標にして「日々の生活の中に教えを実感して、霊魂を浄めていこうと、生活そのものが信仰となっていくこと」を信仰の根本としています。
教理を知っただけでは自然社の信仰をしていることにはなりません。身の回りの事を教えの視点から見て、教えのまにまに日々を暮らしていってこそ信仰なのです。教えは実行することに尽きます。それ
でこそ神の恵みに浴し、幸せに順調に過ごしていけるのです。
苦痛を尊いきっかけに
人生は楽しいことばかりではなく、病気やけがなど肉体的な苦痛や、仕事の行き詰まりや失敗、家庭の不和など人間関係の不調や、交通事故や天災地変など、物質的にも精神的にも様々な苦痛が生じてきます。
「困った時の神頼み」と言いますが、信仰の目的は困り事、苦しみから逃れるためにあるのではありません。自分の身に起きた問題を単に苦しみや不幸と受け取るのではなく、これを機会として自分がより良き、より高き生き方に進んでいくことを、ここで身につけていこうとすること。これが自然社の信仰です。
自然社では、身の上に起きてきた苦痛は、自分の生き方や、自分の心のあり方によって起きてきたものである、と教えられています。そして、その苦痛(「みしらせ」)は自分の心のありように気が付けば解消します。
自分のどんな心が苦痛の元なのかということではなく、自分にはどんな心があるのかをはっきり知って、それを素直に認めれば苦痛は解消するのがこの世の道理なのです。
苦痛を受けるのは不幸なことではなく、自分が生まれ変わるためには無くてはならないきっかけです。苦痛の本当の意味を知り、それを十分に生かしてより大きな幸福の糧にするところに、自然社の信仰の特徴があります。
◎
真の生き方を知って、世のため人のために働き、幸せを得ていくこと、そして、人間の本体である霊魂の浄めを頂いていくところに信仰の目的はあるのです。
このような生き方を知らないでこの世を過ごすことは、それこそ尊い人生を意味なく過ごす、もったいない生き方であり、もったいない人生ではないでしょうか。