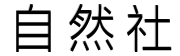今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成17年 6月号 ある日の演壇から
花粉症に思う
森山 勝
今春は花粉症に悩まされた人が多くありました。昨年の夏は猛暑でスギ花粉の成長が促進され、この春は例年に比べて何倍もの花粉が飛散したためでした。
本宮にもスギやヒノキが多く、春先のよく晴れた日には、風が吹く度に黄色の煙が沸き立つように舞い飛ぶのを見ます。この光景を初めて目にして山火事と思って消防署に連絡する人も少なくないとか。
天気予報と一緒に花粉の飛散予報も流され、春の風物詩となった感があり、街を行く人のマスクで防御する姿が目立ちます。そんな様子を見て、花粉症と縁のない人も憂い心から発症することもあるのではないか、と思います。
◎
花粉症は180年程前にイギリスで初めて患者が
発見され、その存在が知られるようになりました。日本では昭和39年に栃木県で最初の報告があり、今では国民の10人に1人、東京では5人に1人が発症していると言われています。
症状には個人差があり、くしゃみや鼻水がとまらなくなったり、目がかゆくなったりするのが一般的です。これは花粉が目や鼻から入ると、体内から排出しようとする抗体反応が起こるためで、それが旺盛な人ほど症状も活発です。
ようやく冬を乗り切り温暖な時候を迎えたのに、花粉症の人は外出もできない、うっとうしい時期となりました。3月にピークを迎えたスギ花粉が4月に入って一段落したら、今度はヒノキ花粉が飛び始めるのでまことに厄介です。
花粉に悩まされる人たちは様々な工夫をしておられるようで、市販薬やマスクの使用はもちろん、ヨーグルトやお茶など、良いと言われるものを食べたり飲んだり、色々実行しておられるようです。
何でも食べ、何でも触れる
花粉症について医師や研究者が言われている対策
は「花粉と接触しない」「ストレスを上手に解消しよく眠る」といったことで、これといった決め手に欠けるようです。
ところが研究者の一人は、「花粉症は現代病で、何でも食べたり触れたりしていた時代にはなかった病気だ」と発表し、それを実証するため、自らの胃腸に寄生虫を飼う実験をしておられるといいます。
そんな突飛な行動にはついていけそうにありませんが、この博士の言わんとすることには見過ごしにできないものがあると思えるのです。
◎
現在私たちが口にする食品は、加工されたものが多く、野菜などの生鮮食品にしても、化学肥料を使用し、水耕栽培という土壌もなしに育った無菌の野菜が当たり前になってきています。
これは私たちが非常に清潔なものを好むようになったことから、生産体制も変わって今日のようになったのです。
買い入れるときも、見た目の鮮度と共に賞味期限
の表示にこだわる人も多くあります。しかし博士の言葉から導き出される答は、きれい好きや潔癖性も程々にすべきだということでしょう。
科学的な因果関係は今後の研究に委ねるとして、自然社の教えでは、健康維持には色々な食品を好き嫌いなく、バランスよく食べることが大切で、これが自然な姿だと教えられています。
しかし今の日本は、偏食という言葉が死語となるほど、好き嫌いという我がままを覆い隠す「グルメ」の風潮が蔓延して、そのぜいたく好みによって飽食しながら飢餓感をつのらせています。
受け入れる心に
嫌いな物や苦手な事を遠ざけて、好きな物や得意な事しか近づけないようなことをしていると、だんだんと自分の身の回りが狭くなってしまうのは当然です。
身の回りを清潔にという意識が過剰になって、汚れているとか不潔と思えたりする異物に過敏に反応しすぎて起こってきたのが花粉症です。花粉症はそういった意味の「みしらせ」なのです。
花粉は私たちの生活の中で本来嫌うべきものではなく、排除すべきものでもありません。自分の狭い感性に合わない異物を気にするあまり、花粉を「敵」にしてしまったのです。
症状が出ている人はもちろん、まだ出ていない人もそのことを知って、目にも見えない花粉に心配したり恐れたりせず、せめて平気になって共存していく許容力を育てていきたいものです。
好き嫌いはだれにもある感情ですが、食生活に限らず人や物などすべてに対して表れていて、嫌いなものを排斥する思いによって抗体を作り苦しむことになっていることを知って、受け入れる心に目覚めていきたいものです。