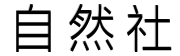今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成17年 4月号 真理の展望
このようになりたい、と
谷田 勲
一昨年の春から、通勤途中にある小学校の近くの交差点で交通整理をしている人たちがあります。午前八時半までの小一時間を、数人の人が交差点で黄色い旗を持って立っておられます。
学校の前の道はこの近辺では数少ない東西に走る二車線の道路で、登校時間には会社へ急ぐ車がかなり通ります。私は毎朝その交差点を自転車で通ります。そこはかつて苫ヶ硲と言われた所で、二車線の道路は谷の底を通り、これに交わる道は北側も南側も下り坂になっています。
始業時間ぎりぎりにこの交差点を通る子供たちが、急いで学校へ行こうと注意をおこたって、坂道から勢いよく道路に飛び出したら…。そんな事故の起こらないようにということで始められたのでしょう、学校が休みの日以外は夏も冬も、毎日同じ人を見かけます。
ここを通る時いつの間にか「おはようございます」と挨拶をするようになりました。この方たちが旗を持って子供を制止したり通らせたりするだけでなく、「おはよう」と声をかけたり、交差点を通り過ぎた後も車が近づいてきたりすると「道の端に寄りなさい」などと注意したりしている様子に、私も自然と挨拶をするようになったのでした。
小学校から頼まれてやっておられるのですかと尋ねると、いやボランティアと言うか、この地域の仲間で話し合ってやり始めただけのことです、とのことでしたが、七十代と見える方たちが一日も休まないで交通整理に立っておられるのは、自発的であるからこそではないかと思います。
ここを通る時、多くの人が交通整理の人と挨拶を交わしています。小学生たちに声をかけるだけでなく、ここを通る人みんなに、ちょっと待ってくださいなどと声をかけているうちにお互いに挨拶をするようになったのです。こうして小学校の隣にある短期大学に通ってくる教職員や学生、介護施設の職員さんなどと交通整理をしている人の間に、朝のひと
時のことではありますが「人の輪」といったようなものが出来ているように見えます。
このような淡い人の輪ではありますが、小学生たちは交差点を通る時に交通整理の大人の方と朝の挨拶を交わすことを通して、周りの人に挨拶することをおぼえるでしょうし、人と人とのつながりが出来ているところでは変な事件や事故も発生しにくいのではないかと思います。
− ◇ −
「世の中に誠ひとつの宝持てなりとゝのはぬものなかりけり」
「誠もて成らざるなしと宣らしたるみ祖のむねを吾生きぬかん」
と聖歌と奉答歌にありますが、「誠を尽くす」ということは、どうすればそれができるか、説明しがたい中身を持った言葉だと思います。
ボランティアの方たちを見て思ったのは、ご本人たちは少しも意識しておられないでしょうが、毎朝変わらない様子で同じ場所に立つということは、よほどはっきり心を決めておられるのだろうというこ
とでした。
朝の一時間を交通整理に立つだけのことかもしれませんが、毎日同じ時間にそこにいて、それが当たり前になっていると言えるほど当たり前の存在…。この姿の中に私は「誠」ということを感じます。ご本人たちにそんなことを言ったら「アホなことを言いなさんな」と笑われてしまうでしょう。でもそれが誠というものの一面ではないでしょうか。
そして、誠を尽くすには自発的な意志で行うということです。
仲間があるとは言っても、寒いときも暑いときも雨の日も毎朝交差点に立つのは、そう易しいことではないと思います。それができているのは、地域や子供たちのことを思う自然な気持ちがあるからでしょう。
子供たちに声をかけたり通る人と挨拶を交わす姿の中に、ここは自分たちの町であるという誇りや、この地域に長く住んできたという感謝が湛えられているはずです。殊更にそんなことを思われたことはないでしょうが、この心が「毎朝休まず」という形
に表れているのだと思います。
− ◇ −
「こんなに真心を尽くしているのに分かってくれない」と思っているような「誠」よりも、当たり前のこととして、なかば楽しみながらやり続けていることの中に、気負いも、てらいも、負担感も、文句を言いたい気持ちもない、軽々として味わいのある誠がこもっています。
だれもが気軽に挨拶できるような心で交通整理をしておられるから、みんな安心してこの交差点を通ることができます。このような軽やかな心でやっておられのは自発的な行為だからこそでしょう。「一生懸命交通整理をやっています」というような気持ちだったら、通る人と気軽に挨拶ができるどころか、無理をして渡ろうとする人を不足に思ったりするのがオチで、そこに人の輪(和)が出来ることはないでしょう。
誠を尽くすには一生懸命であることが必要なときがあると思いますが、それだけでは人の心に通じるような誠にはなりにくいと思うのです。
− ◇ −
自然社で「みそぎ」(心の浄化を願って自然社本宮や教堂で行う勤労奉仕)をするとき、神前で「…何事も進んで喜んでさせていただきます…」と祈ってから行いますが、この気持ちに心からなりきることは難しいことです。しかし、このように祈ってやり始めることで、進んで喜んでやれていない自分の姿に気付くことができます。
心を浄めていただきたいと願って勤労奉仕をしているのに、あの人は自分ほど一生懸命やっていないと不足を思ったり、こうやればうまくいくのにと批判したり、「何事もただに喜んで」やるとか「させていただく」という気持ちからほど遠い心で作業をしていることがあるものです。これは一生懸命やろうとか、進んで喜んでやろうとする気負いが、かえって横道にそれさせてしまうことになっているということかもしれません。
しかし、一生懸命やっていなければこのような心の中のズレに気付くことはありません。そして、作業をしながら「自分はこんなときに、こんな思いを
するのか」と気付かせていただけるのは、「みそぎ」をさせていただくという心で、神様を念頭に置いているからです。
自発的な意志でやるとき、一生懸命であることと謙虚であることを両立させることができます。しかし、自分から思い立って「自発的に」やっていても、てらいや気負いがあると、両立はできないでしょう。
そこに自ら喜びとするものを見つけるか、自分でもお役に立つことができそうだというような、打算や利己心を離れた目的感を見つけたとき、謙虚に一生懸命にやることができるのだと思います。
これが神様を頂いてやるということではないでしょうか。
− ◇ −
信仰とは自分を縛ることではないと教えられていますが、「みおしえ」で教えられたことを自分に強制するような思いで「実行」しようとして、信仰精進を苦しいものにしていることがあります。
しかし、苦痛を抱えた現実の上に、さらに精神的
な苦しみを加えるような精進を自ら強いるのは「みおしえ」の本意ではありません。
心に神様を頂いて、「このようになりたい」という明るい軽やかな気持ちで「みおしえ」をお誓いしたとき、今までと違った視点から自分を見ることができるようになります。
こうして強制されるような気持ちを脱して、自分をもっと優しく、もっと厳しく見つめ、暑いときも寒いときも雨の日も、倦まず弛まず信仰を続ける力を養いましょう。自ら進んで行い、喜びをもってやるところに、人の心にふれる、中身のある信仰をさせていただく道があります。