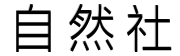今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成17年 1月号 仕事に学ぶ
ボランティア
森山 勝
十月二十三日、新潟県を襲った連続地震は県内の広い範囲で家屋が倒壊し、多数の死傷者が出ました。上越新幹線が脱線し、集落を結ぶ道路は崩落、ライフラインが寸断するなど甚大な被害をもたらしました。
そしていつまでも続く大きな余震のために一時は十万人を超える人たちが避難生活を余儀なくさせられました。
今回の地震の中心部では阪神大震災に並ぶ震度七を観測。「天災は忘れたころにやってくる」と科学者の寺田寅彦は名言を残していますが、今回は忘れる間もありませんでした。
しかしこのような再三の被災経験は悪いことだけではありませんでした。阪神大震災で積んだ尊い体験によって、新潟に救援に向かう政府の対応は初動から素早く、教訓がそのまま生かされていたからで
す。
それに加えボランティアに駆け付けた人たちも大勢でした。そして神戸で培ったボランティアの様々な技術が混乱の中に発揮されるのを見聞きし、頼もしく感じられました。
…※…
ボランティアは定まった職業や業務ではありませんが、不時の災害に行われる様々な救援活動では、ボランティアの役割は今やなくてはならないものとなりました。
今回も被災者は避難所や自家用車で寝泊まりをしました。その後も余震が頻発するため、「傾いた自宅には恐くて帰る気になれない」という声は切実でした。そのため避難直後はみんな一緒にいました。
しかし、避難生活が長期化すると「温かいものが食べたい」「入浴したい」とか、避難所の不自由な生活から、プラバシーが守れるより落ち着いた環境を望む声が聞かれるようになっていったのも当然です。
これらの一人ひとりの声に応えていくのは行政ですが、人手がなく対応には限度があります。そこで力を発揮したのがボランティアでした。被災した人たちの求めに応じ、壊れた家の中の片付けや炊き出し、救援物資の運搬と配給などきめ細かな働きかけや、不安感を訴える人たちには励ましの言葉をかけ、元気づけるなど様々に活躍しました。
…※…
ボランティアは無償の奉仕活動で、あくまで自主参加ですから、ふだん携わる職種とは違った仕事についた人も多く、本来は不慣れな仕事であることも考えられます。しかし、雑用とも言える仕事にも、ボランティアは生き生きと取り組み、被災者から頼りにされ、感謝されたようです。
こうした仕事に取り組む心の姿勢や中身は、日常に携わる仕事への取り組み方とはどうしてこうも違うのか興味がそそられます。
それらを検証するための資料として、阪神大震災の時に参加したボランティアの人たちの記録が参考になるのではと思われます。
阪神・淡路を襲った大震災は、多くの人に色々なことを考えさせました。その一つとして、老若男女を問わず、被災者の元に全国各地から多くの人たちが駆け付けたことが挙げられます。
みんなが「居ても立ってもいられない。なんとかお手伝いができないものか」という純粋な気持ちが、多くのボランティアを突き動かしたのです。それこそ被災地の人たちの痛みや苦しみに対する共感でした。
そして後日、それらの参加した人たちは、「被災地の色々な救援活動を通して、初めて自分にある可能性を知った」「社会的な視野が広がった」「新しい自分を発見できた」と感想を話していました。
…※…
そうしたことを考え合わせると、「他者を生かすこと」が「自分を生かすこと」なのだと結論づけられます。
「はたらく」とは「端を楽にする」ことだと聞いたことがあります。これは単なる語呂合わせかもしれませんが、案外私たちの仕事の本質について的を射
たものでもあります。
ふだんの働きぶりとボランティアの時との違いは、「他のために」という気持ちの純粋さの度合いの違いではないでしょうか。職場で働いているときにはない切迫感が、責任感や義務感をうんと押し上げてくれるのだと思います。
「神訓」第十九条に、「幸福は己を捨つるにあり」とありますが、私たちは他者のために役立つ、そういう働きを通して人として成長し、向上していくのだと思います。