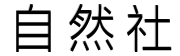今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成14年 8月号
八月十五日の絶食
−・−
八月十五日はアメリカを主体とする連合国軍の攻撃に耐えられなくなって、日本が降伏を表明した日である。
日本は長く続いた戦争で、三百五十万人にものぼる軍人や民間人の戦没者を出した。戦争のために亡くなったのは特別な人ではなく、私たちの親兄弟であり、その知人たちであり、近所に住んでいたごく親しい人たちである。
今はもう戦争を記憶している人は少なくなったが、戦争の悲惨と、国のため、家族を守るために戦いに出ていかれた、近しい人たちの勇気と愛は、多くの人の心に生き続けている。
小泉純一郎総理は、苦しい時には特攻隊で亡くな
った人のことを思うと自分の苦しみなど何でもないことに思えると話しておられる。
野党や外国の要人の反対表明にも揺るがず、八月十五日には靖国神社に行く意志を変えない心の内には、政治的な思惑よりも、人間としての総理自身の、戦争で亡くなられた方たちへの深い思いが強く働いているようだ。
○
ある大学教授から、我が家では八月十五日には、その日一日中食事をとらないことにしていると、かつて聞いたことがある。
そうやって戦争で亡くなられた方や、戦争の悲惨さを思って当時を偲ぶことを、中学生だったご子息たちもよく理解されて、一家そろって食事を絶つという大事な行事を、もう何年も続けておられるということだった。
時に絶食することは体に良いということと、ひもじい思いをすることは精神のためにも必要だということで始められたということだったが、日本人として、戦時中の困窮の、その一部でも肌身で感じることを求める気持ちがあってのことだったと思っている。
学問研究の目的は、大まかに言って物事をより深く広く解明し、人と社会に寄与するところにある。
そのために学者は心身を削って研究を重ねておられる。学者としてそうした生き方をしていく中で、多くの人が困窮に耐え、死を余儀なくされる中で心ならずも国のため身を捧げた時代を、心に深く思うことは、避けて通れなかったのではないだろうか。
戦時色一色に塗りつぶされて、男児たる者が戦場
に赴くことは当然とされる中にあっても、家族と別れ、妻子を残し、一人出ていくことは、たとえその家族を守るためと自分に言い聞かせて、納得したつもりであっても、悲痛の極みであったに違いない。
平時の平和な中でどんなに命を削る思いをして尽くしているとしても、また、そのために精神も肉体も疲労困憊しているとしても、生命そのものを危地に曝すわけではない。
しかし戦地に赴いた人は、心身を尽くすという精神の昂揚や充実感を味わうこともなく、自分の働きだけでなく、生命までも国(社会)のために捧げることを余儀なくされた。
教授は、その思いの一端でも味わうために、八月十五日を絶食しておられたと想像する。
しかし、戦時中を過ごした方への思いやりだけで
、何年も続けて「その日」の絶食ができるだろうか。
世の中のために尽くす使命をもつ学者として、心ならずも国のために死んでいった人への敬意と、ある種の畏れを感じるからこそ、愚直とも見える行為を長年にわたって続けられるのだと思う。
小泉総理は「聖域なき改革」を掲げて政局に立ち向かっておられる。政界、官界、財界ばかりか、これを押し進める過程で広く国民に犠牲を強いることになる改革を進めるには、政治家としての立場にこだわっておられないところに立っていることを自覚し、失敗を恐れたり、安易に妥協することがあってはならないと自戒しておられるであろう。
小泉総理は、国の行く末に与る者として、国のために死ぬことになった多くの方たちに対する敬意と共感によって、財政をはじめ行政を正常に戻すための「聖域なき改革」への強い思いを支えておられる
のかもしれない。
○
我が自然社では、昭和二十三年より平和を祈願する式典を月毎に行い、昭和三十年からは戦没者慰霊月次祭を行ってきた。
これは戦後五十年を迎えた平成六年まで続き、その後は毎月十五日に戦没者慰霊祈念をし、八月十五日には戦没者慰霊祭並に世界平和祈念祭を行っている。
また自然社本宮においても以前と変わりなく毎月式典を行い、九月十九日には年に一度の大祭を仕えている。
我々が戦没者の慰霊に心を尽くしているのは、戦没者の御霊たちが国のために尽くされた至誠を讃え、感謝して、酸鼻を究めた状況の中で亡くなられる
に至った様々な苦しみから解き放たれて、御霊としての修行をしていける状態に鎮まられて、残された家族のため、また国の安泰や平和のために働いていかれるようになっていただくためである。
この祈りは第一には戦没者の御霊に鎮まっていただくためであり、御霊たちに国の安泰のため平和のために働いていただくためであるが、私たちはこの祈りを通して国や人に対する思いを深め、また自分が生かされている意味を広い視野でとらえることに努めている。
それが信仰によってよりよく生きていくために欠かせないことであると信じている。
○
戦没者を思う気持ちを持つことは、人間として当然かつ必要なことであり、慰霊のためにどこに参拝するかは、政治的な意味という卑小なところで論じ
ることではない。
我が国は敗戦による心の痛手と、戦争を忌み嫌う気持ちから発した戦争観が、長らく思想、言論の主流をなしてきた。そのために、戦争で亡くなった人を祀ることについて、政治的な思惑まで絡むことになってしまっているのは、まことに残念なことである。
そのような政治的な思惑をもって対立しているためか、戦没者の慰霊について外国から干渉されたりするが、近隣諸国の危惧は誤解以外のなにものでもない。
我々日本人は戦争の悲惨を忘れてはいない。自分の家族や国内についてのことだけでなく、近隣諸国にその惨禍を及ぼしたことも忘れてはいない。
総理大臣がどこに参拝しようと、それは決して軍国主義の時代を賛美するためではない。
国のために亡くなった人に感謝を捧げ、その精神を讃えると共に、多大な災禍をもたらす戦争の愚を繰り返さないためであり、またそのことを通して、日本が毅然として生きることを心によみがえらせるためである。
毅然として生きるということは、周りにいたずらな対立心を持ったり、自分の都合を立てて無理を押しつけたりすることではない。
目標をはっきり見据えて生きる中から、節度を知り、周りと心から和して、周りのために自分が尽くせることを尽くしていくことを目指してこそ、毅然たる生き方となる。
戦没者の慰霊は、こうした意味でも、極めて重要なことなのである。