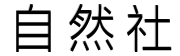今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成14年 6月号
水はどちらに流れる
−・−
今は土のままの道路や空き地を見かけることはまれで、泥んこ遊びをしている子供たちの姿を見ることはほとんどなくなりましたが、私の子供のころは皆がよくやっていました。
そして雨上がりには、こんな遊びをしました。水たまりの所に傘の先を入れ、そこからもっと地面の低い所に向かって線を引きます。
すると水たまりの水が線に沿って流れ始めます。しかし線の掘り方が少ないと途中で止まってしまいますので、何度も何度も線を引きます。そのうちに、見事に川が開通して水がしっかり流れていきます。
水たまりが大きいときには、もう少し手の込んだ
遊びをしました。いったん出来た川に支流を作ります。
はじめのうちは、支流は細々としか流れませんが、支流の方の掘り方を深くして、分かれ目の所で幅を広くしてやると、水は支流の方に勢いよく流れていき、今まで本流だった方は枯れていきます。
雨上がりの下校の道は、楽しい遊び場でした。
どうしてそんな昔のことを思い出したかと言うと、心癖のことを考えていて、ふと、あの小さな川の支流のイメージが湧いてきたからです。
○
自然社で「心癖」というのは、ある場面に出くわしたら自然に出てくる偏った心、自分にとって、また他人にとって不都合を生み出してしまう心のことです。その心が自分の態度や行動を決め、また体に
も影響を与えています。
同じ場面に置かれても、他人は全く異なった心の動きをし、そして言動もまた全く違うかもしれません。
一つの刺激に対してどのような反応をするか、それは元々無限にあるはずなのですが、人間はある決まったパターンでしか反応できないものを持っており、それもはなはだ具合の悪い反応をしてしまうわけです。ついそちらの方向に進んでしまう、それも「これではいけない」と知っているはずなのに、よくない方向に心が動いてしまう…。
そのことを考えていて、水たまりから流れる水を思い出したのです。
水は四方を見渡して、ずっと先の方に排水口があるからそちらへ流れていこう、と決めているわけではありません。ただ引力のままに、すぐ隣の低い方
へと流れるばかりです。だから傘で線を掘ると、そちらの方に流れていきます。
川も最初は小さな緩やかな水の通り道に過ぎなかったでしょう。しかし、いったん通り道が出来てからは、水はそこばかり繰り返し繰り返し流れ続け、やがて深い谷を作り、とうとうと流れる川になり、海に至ります。
私たちの心癖はまさに川です。トラブルという海が待ち受けているとも知らず、当たり前のようにそちらに流れていきます。繰り返し流れ続けることで、少しずつ大きくなっていきます。
何度も失敗をして、こんな心になってはいけないと重々知っているつもりでも、いざ雨が降ると、その瞬間は先のことをすっかり忘れ、いま最も心地よい自分に合った道を選び、そして例の海へとまっしぐらに進んでしまうのです。例えば、甘い物を食べてしまったり、酒を飲んでしまったり、腹を立てた
り心配したり、その時はそれしか道がとれないかのようにそうしてしまうのです。
さてそこで、どうすればこの川の流れを変えられるかです。そのことを思いめぐらせていて、まさに水たまりの川作りに似ているな、と思ったわけです。
傘の先で線を一回引いて、流れが変わればしめたものですが、そう簡単には変わりません。
しかし一回分は確かに新しい道筋が刻まれました。十回引いたら少し水がそちらに流れるかもしれません。でも元の川が太くて深かったら、大筋に変化は現れないでしょう。でも百回引き、いつしか千回繰り返せば、必ず流れが変わってきます。
自分にはこういう癖があるのだとはっきり自覚すること、そしてこの癖はいらないときっぱり決意すること、これが流れを変える工事です。
無意識に繰り返す癖は、ちょうど川が土を削るように少しずつ少しずつ成長しますが、一方自覚をし、決意をする力、つまり意識して物事を行う力は、人の力で土を削るように、ずっと大きな変化をもたらします。ですから決意を重ね自覚を深めることで、どのような心癖も変わらないものはありません。
ただ、それでも時間は掛かるでしょう。無意識とは言え、「心癖」は長い長い年月繰り返してきたものですから。