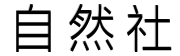今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成13年 3月号
日本の国の中心
−・−
去る五月、森総理大臣は神道政治連盟国会議員懇談会の席上の挨拶の中で「日本の国は天皇を中心とした神の国である」と発言して、問題となりました。
新聞や野党は「国民主権に基づいて国会で選ばれた首相が、自らその根本原理を否定するような発言を行った。
事態は深刻かつ重大である」そして「国の基本的なルール、原則にかかわる事柄だ、そこを不用意に踏み外せば日本の国際的な信用を損ねる」と、この発言を痛烈に批判しました。
総理がどのような意図でこの発言をしたか定かではありませんが、伝えられるところによれば、神道
政治連盟へのリップサービスではなかったかということです。
仮にこの発言が、単なるリップサービスであるとするならば、大変に遺憾なことだと思います。
というのは、神とか天皇というような日本の国の根幹に関わる重大かつ神聖な事柄は、軽々しくリップサービスに使うようなことではないと思うからです。
しかし、総理の意図はどうであれ、結果としてこの「神の国」発言は、日本という国の個性というか体質を端的に表現したことによって、私たちに、日本人が古来から連綿として受け継いで来た価値観や国柄について、改めて問題を提起したことになったのではないでしょうか。
戦後の五十年間、経済の発展に力を尽くした首相は何人もありましたが、思想や道徳や文化や歴史な
どについて、確固とした理念や哲学をもって国民をリードした総理はほとんどなかったのではないでしょうか。
戦後の復興に続く高度経済成長と、物質的に豊かな国造りを指向したのは良かったのですが、国の伝統文化を政治に反映しようという理念を持った総理は、残念ながらほとんどなかったように思います。
そう考えると、今回の総理の「神の国」発言は、結果として素晴らしい問題提起であったと思います。
○
この「神の国」発言に対して、マスコミ、特に新聞は敏感に反応して大変な騒ぎを引き起こしました。
そして野党各党も、その依って立つ政治哲学の違
いから批判の角度に
違いはありますが、天皇が中心であるというのは国民主権に反する、という見地から一斉に批判の矢を放ちました。
例えば、批判の中に「日本を『天皇を中心とする神の国』とみなす発言は、どう弁明しても、憲法の国民主権の原理と相入れない」という意見がありました。
これは一見もっともな意見であるかのようです。
しかしこの思想の根底にあるものは、天皇と国民とは国政の権力を争う関係にあって、その争いの結果国民が勝ちをしめるのが「国民主権」であるとする考えです。
たしかに、そのような天皇と国民を対立的にとらえた考えの上に立てば、「天皇を中心とする…」と
いう言葉は「国民主権」と相入れないことになるでしょう。
しかしこの天皇と国民を対立的にとらえる思想は「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と定めている日本国憲法第一条と明らかに矛盾しています。
日本国憲法の国民主権は「天皇を中心とする」という言葉と相入れないことはありません。
天皇は象徴であることによって、日本の国柄がはっきりと分かるという大切な「はたらき」を果たしておられるのです。
我が国は長い歴史を通して、国民の統一、国民の総意は、いつも天皇において表現されてきました。「天皇中心の国」であるという発言は決して国民主権に反することにはならないのです。
総理の発言を批判する人たちは「日本は国民主権国家であり、天皇は単なる国の象徴であるのに、首相の発言には天皇主権のような響きがある」と言っているようです。
つまり「象徴」とは、なくてもいい無意味な存在と解釈しているのでしょう。
しかし、この「統合の象徴」は「国の中心」を意味していると言っても言い過ぎではないでしょう。
私たち日本人は戦後、国の一番の根幹に関わるこの大切な問題を突き詰めて考えることを避けて、真剣に議論してこなかったのではないでしょうか。
日本国民が避けていた問題を、森総理は突然、核心を衝く形で問題提起したのです。
○
「国の中心」ということが問題にされましたが、国家だけでなく、何か一つの集団が存在しているということは、そこに中心の存在があるということです。
中心はその周辺を一つにまとめ、一つの物事としてのはたらきを生かし、より高めていくという「はたらき」をしているのです。
中心と周辺と言っても、二つのものがあるのではなく、元々一つの物事が成り立っていく上での、内面的なはたらきの状態を言っていることですから、中心はすなわち全体を意味しており、周辺は中心のはたらきと一つとなって全体を形成しています。
ここで言う中心の「はたらき」とは、政治的な次元を超えたものであることは言うまでもありません。
日本の歴史を一筋につながったひもとしてみれば
、天皇が直接政治に関与しなかった時代の方がずっと長かったにもかかわらず、天皇が国民統合の中心であったことには変わりありません。
森総理が言おうが言うまいが、有史以来今日まで日本は天皇を中心と
した国家であったのです。
我が国は神話の時代から、天照大神が初めて農業と養蚕の道をひらいて、人々を飢えと寒さから救われたのが出発点とされており、歴代の天皇が、病気の治療法や、治水事業や、飢饉の備えと国民の福祉に努めてこられました。
そして、古来、天皇が国民を「おおみたから」と呼んでおられたことをみても、天皇と国民の間柄がどのようなものであったかが分かります。
その一例として、日本書記の仁徳天皇について書かれたくだりに、ある日天皇が高台に上って見渡さ
れたところ、民の家のかまどから煙が立ち昇っていない、これは民が疲弊しているからだと三年間課役を廃止された、というエピソードが書かれています。
現代の歴史学では、仁徳天皇の実在は証明されがたいとされていますが、たとえこれが伝承にすぎないとしても、私たちの先祖は天皇と国民との間柄をこのようにとらえ、これを理想としてきたと言えるのではないでしょうか。
このような民を愛し民を尊ばれる天皇のお心が、国の安泰とまとまりをもたらしてきたと言えるでしょう。
時代が下って、武家が政治の実権を握っていた時代、将軍がいかに大きな権力を握っていても、国民は権力を持った為政者として認めたのみでした。
そしてこの時代、歴代の天皇は京都の御所にあっ
て国家の安泰と国民の安寧を祈っておられたと伝えられています。
そして、江戸時代の末に外国の刺激によって国民が「一つの国民」としての存在を自覚したとき、私たちの先祖は、ただ天皇においてのみ国民的統一を考え、意識したのでした。
これに関して「古寺巡礼」や「風土」の著作で知られている和辻哲郎氏は、「わが国の歴史において実に希有というべき英雄が輩出した時代にも、なお天皇がそれらのうえに立って国民の統一の表現者としての権威を保持し続けたという事実は、きわめて教えるところが多い」
「むしろ実権のない皇室に権威が保たれ、その権威が実権のあるものにも不可欠のささえとなっていたことに、大きい意義を認めるものである」と、明快に述べておられます。
○
我が国が「天皇を中心とした国」であるということは、歴代の天皇が武力をもって国民を統治してきた権力者ではなく、国民を愛し、国民のために尽くしてこられたということです。
私たちは連綿と伝えられてきたこの素晴らしい国柄をもって、私たちの文化を世界に発信し、世界の平和に大きく貢献いきたいものであると思います。