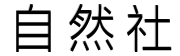今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成12年12月号
体を大切にする
−・−
「体を大切にする」ということで、自分の日常生活を見直してみたら、何かの理由をつけて夜更かしをしたり、好きな物はついつい食べ過ぎたり、飲み過ぎたりしていることが多いことがわかった。
今や二人以上の人が寄ると必ずといってよいほど、病気や健康に関する話題になるという「健康ブーム」である。
私も人並みに健康でいたいと願っているが、一方では前述のように体に無茶をさせるようなことを平気でしている。そしてそれが体をこわす元になっている。
病気になる前は体力が徐々に低下しているのか、ふだんとは体調が微妙に違う。そしてたいがい風邪
気味になる。そこで私の場合、体力や健康の目安になるのは風邪ではないだろうかと思っている。
風邪は昔なら冬の季節に引くものと決まっていたのだが、エアコンなど生活環境の向上のせいか夏風邪を引く人も多い。風邪は「万病の元」と言われてきたように健康の知識も医療体制も整った今も、あなどれない「病気」のようだ。
風邪は感冒とも言ったりするが、なぜ「風邪」と書くのだろうとふと思った。風邪と書けばだれでもカゼと読む。風という一字だけでもカゼと読めるのに、なぜ「邪」という邪魔な一字をわざわざつけたのだろうか。
風邪という字の出典は漢方医学からきた術語の一つらしいのだが、風は突然吹いてきて樹木に当たると梢が揺れ動いたり葉がザワザワと鳴る。
風邪の場合も、突然に頭が痛くなって、体の表面
がザワザワと寒気を感じるというような症状が現れることから、風と一緒に「邪気」を送りこまれたと考えたのだろう。
風邪は引きがけが大事だと言われる。体の表面がザワザワと寒気を感じてクシャミが出た瞬間に風邪気味だと気づいて、体の安静をとるなり、無理している状態をやめれば、まずこじらせたり長引かせたりしないで済む。
このことは、口で言うのは簡単だが、実際に行うことは至難である。なぜなら、風邪になるほとんどの場合、目の前の事に思い患っていて、そのことで頭が精一杯であろうから、自分の体の状態を気づかう余裕などはとても持てないというのが正直なところである。
思い患うことが、仕事上の急いでいる厄介な問題であったり、学生なら試験が迫っていて気が気でないということだったり、目の前の事にとらわれて目
が離せなくなってしまうことにあるようだ。
そこで寒いなあと感じつつ、その寒さから抜け出す手段や、寒さを防ぐ工夫をすら考えられなくしてしまう。その揚げ句、本当に風邪を引くことになる。
話ができ過ぎていると思われるだろうが、この原稿を書いている時、突然ひどい悪寒と食欲がなくなる状態に陥った。流感のようだった。あれこれと忙しさに直面している最中だったが、抱えている仕事をすべて中断して休んでしまった。
半日横になっていたら少し楽になったので、それから仕事に戻り外出もしたが、それ以上症状はひどくならずに済んだ。もし休まずに無理を続けていたら、とても半日くらいの休養では回復しなかったに違いない。この辺りの見極めが大事なのだと改めて思い知った。
風邪をすぐ引くので困るという人がおられるが、考えようによっては、それで自分の健康チェックができることになるのなら幸いだと思ってもよいのではなかろうか。「たかが風邪だ」という気楽な受け取り方と共に、自分の体力回復に努めていける機会が得られたからである。
しかし「たかが風邪」とはいえ「されど風邪」であり、決して油断はならない。年を取ると共に体力が落ちて、全般的に病気にかかりやすくなっている。その前兆としての風邪の症状かも知れないからである。
医学的には確かにそういうことなのであろうが、心と体は一つであると信じる私たちは、心の状態こそが病気に陥っているのであり、それこそが問題にすべきことなのだと教えられている。
それをはっきり知って、こだわりのない素直な心に立ち直っていくためにも、まず「みおしえ」を願
うことである。ただ目の前の苦痛にとらわれて、病気を治すことや、苦痛から逃れることばかりを考えず、病気を通して心の浄化を目指していくべきである。
神訓の二十一条目に「天地の理法にしたがひ身を堅固にせよ」と示されている。
これによると、何事も喜んで受け入れ、周囲のために尽くし、人と和していくという、神の働きと同じ方向を生きていくことが本来の生き方である。勝手気ままを慎み、心身共に健康であることは、人間として自然な姿であると教えられていることを心に銘記しておきたい。