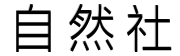今月の言葉 > 自然誌 文章から > 平成12年 9月号
人に左右されないために
−・−
私たちは自分で気付かないうちに人に左右されて行動していることが多いようです。
例えば何かの話し合いをしている時、多くの人の意見や有力な人の意見などによって一つの考えが示されると、その考えに問題点がある場合でも、さらに突っ込んで考えたり議論することはあまりしないで、その場の雰囲気で、何となく大勢に従って全員が賛意を表するようなことになってしまうことが多いのではないでしょうか。
○
私たち日本人は国民性として様々な優れたものを持っています。しかしその反面でいくつかの欠点を持っています。
その一つとして、周囲の人の思惑を気にしすぎて、自分の考えを持っていてもそれを表明しないで、周囲の大勢に従ってしまう、ということがあります。
私たち日本人は他人が自分をどう思うかということに対して神経質に考えて、自分の評価を気にしたり心配したりすることが多いと思います。
最初に例に挙げた、大勢の人や有力者の意見に無批判に従う場合でも、他の人たちの思惑を気にして、はっきり自分の意見を表明できないで、結果として人に左右されることになっているのではないでしょうか。
これは私たちが自己というものをはっきり持っていないからです。
自己を持つというと、己を立てるとか、自我を出す、ということと混同されそうですが、ここで言う
「自己を持つ」と言うのはそのようなことではなく、自分の眼でものを見て、自分の頭でものを考え判断したことを、周囲の思惑などを気にしないで堂々と表現していくことです。
○
黒沢明監督の映画「生きる」は、自己を持たず、周囲に押し流されて生きていた定年間近の無気力な市役所の市民課長の主人公が、胃ガンで余命いくばくもないことを知り、それが切っ掛けで自分の生き方を変えて「積極的に生きよう」と仕事に命を懸けるという話です。
陳情に来た市民のために市の上層部や他の部署の人たちを説いて回り、公園を造ることに奔走する。
そして、その公園が出来上がった時、命が尽きる。「生きる」とはどのようなことかを私たちに鋭く問い掛けた不朽の名作です。
人間が「自己を持つ」ということは、自分の考えに固執することではなく、この映画で描かれているように、自分の生き方にはっきりとした拠りどころを持つということです。
人間は、一人ひとりが神様によって生かされている掛け替えのない存在なのですが、他人の思惑を気にしたり、自分の生き方をしっかり持っていないと人に左右されて生きることになり、神様から与えられている自分の個としての役割を粗末にすることになります。
○
世の中で大きな仕事を成し遂げた人は皆しっかりとした自己を持っています。「あの人は自分の意見をはっきりと持っているから、安心して仕事を任せることができる」ということがよく言われていますが、自分の意見をはっきりと持ち、それを表現していくことは、自我を立て己に固執することとは違い
ます。
世の中は個々の人間の複合体でなく、神様の生命が形をとって現れている一体の姿であり、一人ひとりの性格や容貌が異なっているように、それぞれに個性があり、一人ひとりが掛け替えのない存在です。
ですから、人間一人ひとりの「はたらき」には、それぞれ他の人と異った独自の何ものかがあるのが当然で、世の中には同じ人はなく、どんな人もその人と替われる人はいないのです。
ですから人間が「自己を持つ」ことは、自己を生かすことであり、自分だけにしかない特質を伸ばすことになるのです。
これは結局、世の中を成り立たせるはたらきをより大きくすることであって、反対に自己を持たず、他に追従し、模倣し、屈従し、付和雷同し、人に左
右されることは、世の中を成り立せる「はたらき」をおろそかにしていることになるだけでなく、人間として生きがいのある生活はできないことになります。
人に左右されないためには、自分は何人も替わることができない尊い存在であることをしっかり自覚して、他人の思惑など気にせず毅然として生きていくことが大切であると信じます。